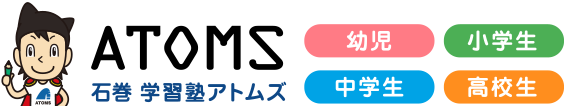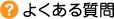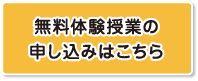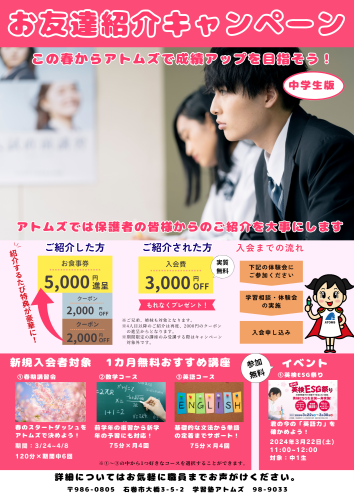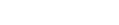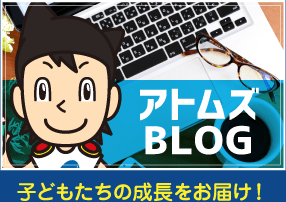2025-03-05 15:32:00
英会話オレコ体験会
![]() 20250308GeT体験会チラシ.pdf (0.84MB)
20250308GeT体験会チラシ.pdf (0.84MB)
2025-03-05 12:45:00
お友達紹介キャンペーン
2025-02-26 20:02:00
春期講習2025
![]() 春期講習のご案内 中学部小学部 2025.pdf (0.33MB)
春期講習のご案内 中学部小学部 2025.pdf (0.33MB)
2025-02-26 19:51:00
アトムズ通信202503
![]() 2025.3.pdf (0.36MB)
2025.3.pdf (0.36MB)
2025-02-26 18:16:00
202503保護者面談
![]() 3月面談希望表2025.pdf (0.09MB)
3月面談希望表2025.pdf (0.09MB)