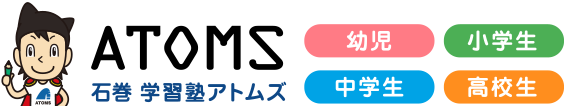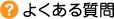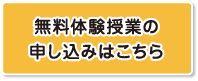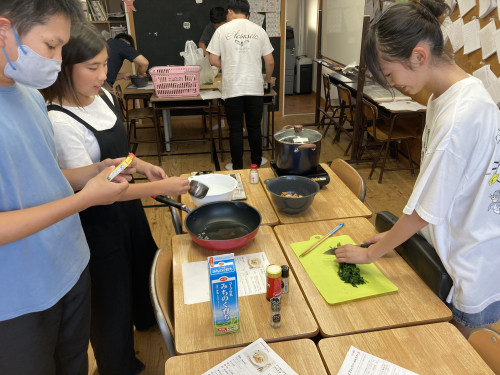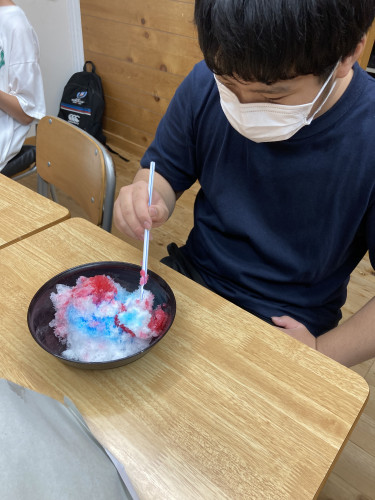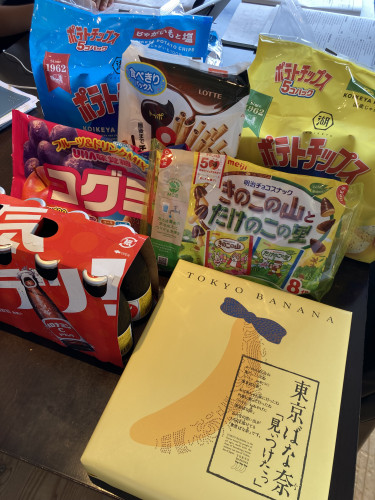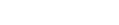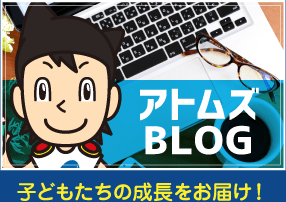サマースタディーキャンプ2025③
9時間目は家庭科!
スタディーキャンプは勉強だけでなく、調理実習もあります。
味の素さんの「勝ち飯」から夕飯メニューを生徒全員の多数決で決めました。
その結果…「ソーセージとほうれん草のクリームパスタ」に決定!
副菜として「じゃがいもとブロッコリーのみそチーズ焼き」と「トマトのバジルマリネ」と「きゅうりの漬物」
学年でグループに分かれて調理スタート。
さてさてどんなお味になるのでしょうか…

とてもおいしい夕飯を食べることができました!!
夕食を終えて、デザートのかき氷を食べて、いざ10時間目、11時間目に突入!
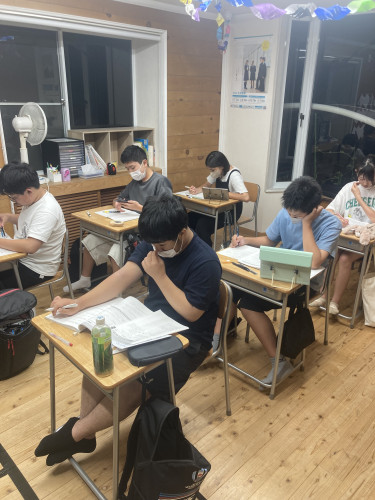
気が付けば、本日のカリキュラムが終了です。
あっという間の1日目でした。今回のスタディーキャンプはお泊りではなく、夜は自宅に戻ります。
明日、朝8時から2日目のカリキュラムが再開します!
本気で勉強に取り組む姿は本当にかっこいい!明日も全力で勉強に取り組もう!!
サマースタディーキャンプ2025②
サマースタディーキャンプ2025①
スタディーキャンプがいよいよ始まりました!

1日11時間の勉強合宿です。「勉強をがんばりたい!」という想いを抱いた中学生が参加してくれました。
ちょうどいま、甲子園では高校球児が熱戦を繰り広げています。もう20年以上前の話になりますが…私も甲子園を目指して本気で野球と向き合っていました。何度も何度も悔しい想いをしてきました。何かに本気で取り組むことは選手だけでなく、見る側にも感動を与えてくれます。勉強も同じです。勉強に本気で取り組んだことはありますか?自信をもってYESと答えられる人は多くないと思います。本気で取り組むことで、家族、学校の先生、関わる人たちが必ず応援してくれます。
朝のホームルームでは、今回のスタディーキャンプの心得を3つ伝えました。
①全力で取り組むこと
②ネガティブな発言をしないこと
③お互いを称え合うこと
点数の良し悪しは関係ありません、一番大事なことは「自分から勉強に向き合うこと」です。アトムズではそんな生徒たちをたくさん育て、応援していきます!
そのためにも、このスタディーキャンプ2日間を通して、生徒たちの心に届くようなメッセージをたくさん伝えていきます!
令和7年度 夏の学力テスト
![]() 2025学力テスト.pdf (0.14MB)
2025学力テスト.pdf (0.14MB)
アトムズ通信202508
![]() 2025.8.pdf (0.42MB)
2025.8.pdf (0.42MB)